数字に見るOFM兄弟共同体
2008年もほぼ半分が過ぎようとする今、概観ながら私たちの「状況」を知っておくのがよいでしょう!2007年12月31日現在、私たち小さき兄弟の総数は15,030人(前年比226人減)です。詳細は以下の通りです:志願者614人(総数に含まれない);修練者387人;有期誓願宣立者1,603人;荘厳誓願宣立者12,033人(司祭10,228人、終身助祭69人、神学生456人、ブラザーの兄弟2,180人);枢機卿の兄弟6人、司教/大司教101人。帰天した兄弟301人。
小さき兄弟たちは世界110カ国に散らばっており、その分布は次の通りです(括弧内数字は前年比):アフリカと中東1,088人(+12)、ラテンアメリカ3,609人(-117)、北アメリカ1,616人(-16)、アジア・オセアニア1,301人(+29)、西ヨーロッパ4,917人(-129)、東ヨーロッパ2,499人(-5)。
普遍的兄弟共同体は、管区103、自治分管区7、従属分管区13、連合1、宣教地区19、管区長協議会14、協議会連合3(アジア・オセアニアのFCAO、ラテンアメリカのUCLAF、ヨーロッパのUFME)という構成になっています。
数字は私たちの生活の質を語るものではありませんが、重要なメッセージを含んでいます。それは私たちについて、また私たちの家族について語っています。そして私たちが直面しなければならない挑戦、すなわち私たちのカリスマの「可視性」、召命の司牧的な世話、文化の促進、私たちの生活とミッションに質を与える方法を共に求めるのに必要な協働等を理解するための一助となります。
福者ヨハネ・ドゥンス・スコトゥス帰天700周年にあたって
イタリア南部におけるスコトゥス哲学:
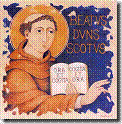 スコトゥスの帰天700年(1308-2008)を記念して、スコトゥス思想の広がりに光を当てる事を目的とした国際会議が、カステラーナ・グロッテのスコトゥス研究センターの主催で3月25日から28日まで開かれました。イタリアを始め各国の様々な大学から、以下の多数の発表者が出席しました:ローマのセラフィクムのオルランド・トディスコ氏、ケルンのドゥンス・スコトゥス・アカデミーのヘルベルト・シュナイダー氏、ローマのマリア学アカデミーのステファノ・チェッキン氏、ランドルフォ・カラッチオロについて発表したフライベルグ大学のウィリアム・デュバ氏、兄弟ディオメデ・スカラムッツィの人物像を例証した研究センター長の兄弟ジョヴァンニ・ラウリオラ。会議の山場はサレルノ大学のフランチェスコ・フィオレンティノ氏による提言で、フランシスコ会士アルンウィックのグリエルモの仕事が明らかにされました。グリエルモは1329年から1333年までの間ジョヴィナッツォ(BA)司教として、教皇ヨハネ22世とナポリ国王ロベルト・ダンジョ及びその妻サンチアの間に起こった争いを仲介役としてとりなし、スコトゥスの帰天後わずか10年から15年で、南イタリアでその学説の存在を立証しました。
スコトゥスの帰天700年(1308-2008)を記念して、スコトゥス思想の広がりに光を当てる事を目的とした国際会議が、カステラーナ・グロッテのスコトゥス研究センターの主催で3月25日から28日まで開かれました。イタリアを始め各国の様々な大学から、以下の多数の発表者が出席しました:ローマのセラフィクムのオルランド・トディスコ氏、ケルンのドゥンス・スコトゥス・アカデミーのヘルベルト・シュナイダー氏、ローマのマリア学アカデミーのステファノ・チェッキン氏、ランドルフォ・カラッチオロについて発表したフライベルグ大学のウィリアム・デュバ氏、兄弟ディオメデ・スカラムッツィの人物像を例証した研究センター長の兄弟ジョヴァンニ・ラウリオラ。会議の山場はサレルノ大学のフランチェスコ・フィオレンティノ氏による提言で、フランシスコ会士アルンウィックのグリエルモの仕事が明らかにされました。グリエルモは1329年から1333年までの間ジョヴィナッツォ(BA)司教として、教皇ヨハネ22世とナポリ国王ロベルト・ダンジョ及びその妻サンチアの間に起こった争いを仲介役としてとりなし、スコトゥスの帰天後わずか10年から15年で、南イタリアでその学説の存在を立証しました。
アジアとオセアニアにおける私たちの存在
アジアは本会の最初のミッションの一つでした。東方を訪ねたフランシスコを始め、13世紀の数多くのフランシスカン使徒たちによる中国・モンゴルへの旅(カルピネのヨハネ、モンテコルヴィノのヨハネ、ポルデノーネのオドリコ・・・)から現代に至るまで、7世紀が過ぎました。現在、兄弟たちは19カ国に散らばり、EAC(東アジア協議会)とSAAOC(南アジア・オーストラリア・オセアニア協議会)の2つの協議会を構成しています。この地域では1989年から2006年までの間にメンバーが325人増加しました。スリランカやタイ、ミャンマー、東チモールのように新しい兄弟共同体が生まれており、後者2つは新しい宣教地区です。2006年に設立されたミャンマーの共同体はベトナム、韓国、インドネシア出身の4人の兄弟たちで出発し、志願者1人と入会希望者5人が加わりました。東チモールの共同体は2008年にインドネシア管区の従属宣教地区として正式に設立され、11人の荘厳誓願宣立の兄弟と7人の修練者、16人の志願者がいて、すでに前途有望な共同体となっています。東チモールのように、長期にわたる戦争と政情不安によって疲弊し荒廃した国における本会の存在は、すでに大変重要で心強いものとなっています。
フランシスカン新刊の栞
(1)アルバロ・カッチオッティ/マリア・メッリ共著「カピストラノのヨハネと教会改革」(原題Giovanni da Capestrano e la riforma della Chiesa)。フランシスカン叢書出版、ミラノ、2008年。全186頁(イタリア語)。 1456年帰天した兄弟カピストラノのヨハネの出来事は、現代に対して並外れて大きな力を持っています。彼の姿は私たちに、根拠が無い上に一元化された解釈や、さらには無意味な固定概念を見直して乗り越え、おそらくは退けるよう求めています。安直な「帰納的」判断と狭量な道徳主義を回避して、この小さき兄弟の著作の中にキリスト教の壮大な計画を浮き彫りにした諸学者からの寄稿を、本書は丹念に取りまとめています;壮大な計画は修道的でしたが、同時に、教会を改革するという目的のために中央ヨーロッパの諸修道会を動員するにあたって政治的にならざるを得ませんでした。
(2)ピエトロ・メッサ著「フランシスコとポルツィウンクラ:『小さく貧しい教会』から天使の聖母聖堂へ」(原題Francesco e la Porziuncola. Dalla “chiesa piccola e povera” alla Basilica di Santa Maria degli Angeli)。ポルツィウンクラ出版、2008年。全504頁(イタリア語)。 「小さく貧しい教会」ポルツィウンクラは、兄弟フランシスコの出来事において重要であるばかりでなく、兄弟たちの中の「兄弟性」の確立において、そして小さき兄弟たちの歴史においても重要でした。それ故に、アシジの小さな田舎の教会が目撃した様々の出来事について本格的な深い知識を得る事は、800年の時を隔てて、これらの出来事の深い意味のみならずその出来事が数世紀の間ずっとどのように記憶され、再現され、祝われてきたかを理解しようと努める人々すべてにとって、必要不可欠の条件です。実にこの「ポルツィウンクラから天使の聖母聖堂へ」は、数世紀にわたる長い旅路です。それはまた「創立時の様々の出来事は連綿として続く歴史そのものでもある」という事が認識できる道程と言えるでしょう。



